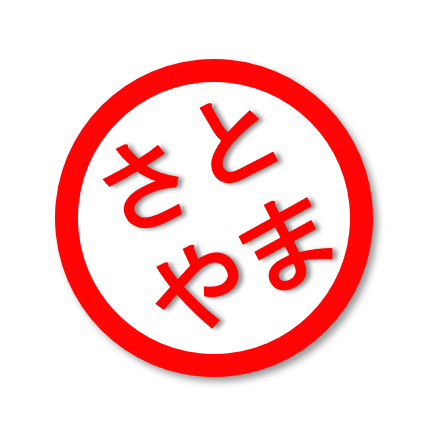活動レポート 2025年度
- 2025年度(このページ)
- 2024年度
- 第12回
- 2026年3月14日(土)~16日(月)
- 炭焼き・きのこ菌駒打ち
レポート未
月例活動レポート 2026年2月14日(土) 炭出し・花炭作り・ピザ焼き
2月の月例活動では、「炭出し・花炭づくり・ピザ焼き」を行いました。
花炭は、缶によっても出来具合が違ったようです。細長い缶はムラができやすく、平べったい缶のほうがよさそうでした。
手作りピザ窯では温度調節が難しかったですが、みんなでいただくことができました。トッピングとソースがなくなり、台だけ焼いてみると、チャパティのように膨らむものも。残った台には砂糖をふりかけて焼いてみました。他にもいろいろアレンジできそうですね。
2月のお便り
長池里山クラブの皆様
2月の活動「炭出し・花炭づくり・ピザ焼き」はいかがでしたか。炭焼きの原理がわかったところで、3月はいよいよ炭焼きを行います。炭焼き当日は汚れることを前提に、服装を工夫しておいでください。また、灰や煙を避けるため、マスクや帽子の着用もお願いします。
電気やガスが使えなかった頃は、木炭は煮炊きをしたり暖をとったりするために、日常生活に欠かせないものでした。農閑期の農家が炭を焼くことが多かったそうです。現在、炭を日常的に使う方は少ないと思いますが、石油が使われるようになる以前は、燃料として炭や薪、柴(焚きつけに使う細い枝など)が用いられていました。
日常生活に必要な燃料を確保することは非常に重要であったため、柴刈りや薪作り、炭材づくりなどを効率よく行うために、たいていの農家には鉈(なた)がありました。鉈は、藪払い・枝打ち・下草刈り・薪割り・竹の加工(割る・削る・細工する)など、さまざまな作業に使うことができ、場合によっては狩猟にも用いられました。そのため、里山の農民にとって欠かせない道具でした。
キャンプで薪やフェザースティックつくりなどに鉈を使う方はいらっしゃいますね。里山クラブでは、主に枝打ちや枝払いに使用しています。興味のある方は、自主活動をのぞいてみてはいかがでしょうか。
*これからの自主活動について*
田んぼ:米作りに向けて、田んぼの荒起こしを行います。
畑:土づくりを進めます。
シイタケなどの榾場(ほだば:栽培している場所):整備を行います。
雑木林:炭焼き、キノコのコマ打ちのための準備を進めます。
雑木林の活動には、安全のため、複数人で協力しないとできない作業が多々あります。人手が必要ですので、継続して参加いただける方が増えると大変心強いです。チェーンソーの使い方やメンテナンス、安全対策についても指導いたしますので、ご希望の方は下記よりご連絡ください。
メール:mail@nagaike.info
お問い合わせフォーム:[こちら](https://nagaike.info/category/contact.html)
自主活動は、火曜・土曜の10:00〜14:00頃に行っています。見学や短時間の参加も大歓迎です!
自主活動についてもっと知りたい方は、里山クラブのウェブサイトhttps://nagaike.info/category/satosigo.htmlをご覧いただき、「さとしごメール」の受信をご検討ください。
皆さまのご参加を心よりお待ちしています。
臨時活動レポート 2026年1月17日(土)・2月7日(土)剪定講習会
「剪定講習会」を実施しました。
さとやま日記にて梅の剪定講習会の様子をレポートしています。のぞいてみて下さい。リンクしています。
月例活動レポート 2026年1月10日(土) どんど焼き・山開き田開き畑開き
1月10日の活動「どんど焼き・山開き田開き畑開き」には、130名を超える多くの方々にご参加いただきました。間近で見る大きな火は迫力がありましたね。
近年、生活の中で直火を扱うことが少なくなりましたので、特に子どもさんには印象に残ったのではないでしょうか。どんど焼きでは正月飾りやお守りなどを焚き上げ、年神様を見送り、火によって厄を払い、お世話になったお守りなどは、感謝して手放します。
人類が火を使うようになった時期は明らかではありませんが、40万年くらい前の遺跡に、炉の跡が残っているそうです。火の使用は様々な恩恵をもたらしましたが、火事のリスクと隣り合わせなのはいつも変わりません。里山クラブでも消防に届出をし、消火の準備を整えています。
どんど焼きの火を思い出しながら、地域の行事の意味や、火の取り扱いの注意など、ご家庭の話題にしていただけると幸いです。
1月のお便り
長池里山クラブの皆様
一年のはじまりに「どんど焼き・山開き田開き畑開き」を無事に行うことができました。ご協力ありがとうございました。
どんど焼きの熾火で繭玉焼きをしましたが、皆様の地域では繭玉を飾ったり食べたりする習慣はありますか。
お正月には、柳のような細長い枝に小さな団子や餅をつけ、たわわに実った稲穂に見立てて飾る地域があります。これは「餅花」と呼ばれ、五穀豊穣を願うお供えです。地域によっては「粟穂(あわぼ)」「稗穂(ひえぼ)」「稲の花」など、さまざまな呼び名があります。島根の神社などでは「もち花まつり」も行われています。
繭玉は餅花の一種で、特に養蚕業が盛んだった地域で、繭の形に似せた団子を作り、豊作を願ったものです。団子は、米粉、ひえ粉、とうもろこし粉などを使って作ります。この餅花、あるいは繭玉を、どんど焼きの火で焼いて厄を払い、それを食べて無病息災を祈願します。
芭蕉の句に「餅花や かざしに插せる 嫁が君」というものがあります。「嫁が君」は新年の季語で、ネズミの異称。夜目がきくことを「嫁」とかけた言葉遊びのようです。
ネズミは五穀豊穣を司る大黒天の使いともいわれています。これは一説には、大国主命(日本では大黒天と同一視されることがある)がネズミに助けられた神話(古事記)に由来するそうです。そのためか、狛ネズミのいる神社もあります。
ネズミは五穀豊穣を司る大黒天の使いともいわれています。これは一説には、大国主命(日本では大黒天と同一視されることがある)がネズミに助けられた神話(古事記)に由来するそうです。そのためか、狛ネズミのいる神社もあります。
*これからの自主活動について*
田んぼ:米作りに向けて、田んぼの荒起こしを行います。
畑:土づくりを進めます。
シイタケなどの榾場(ほだば:栽培している場所):整備を行います。
雑木林:どんど焼きや炭焼き、キノコのコマ打ちのための準備を進めます。
雑木林の活動には、安全のため、複数人で協力しないとできない作業が多々あります。人手が必要ですので、継続して参加いただける方が増えると大変心強いです。チェーンソーの使い方やメンテナンス、安全対策についても指導いたしますので、ご希望の方は下記よりご連絡ください。
メール:mail@nagaike.info
お問い合わせフォーム:[こちら](https://nagaike.info/category/contact.html)
自主活動は、火曜・土曜の10:00〜14:00頃に行っています。見学や短時間の参加も大歓迎です!
自主活動についてもっと知りたい方は、里山クラブのウェブサイトhttps://nagaike.info/category/satosigo.htmlをご覧いただき、「さとしごメール」の受信をご検討ください。
皆さまのご参加を心よりお待ちしています。
臨時活動レポート 2025年12月20日(土) ミニ門松つくり
さとやま日記にてミニ門松作りの様子をレポートしています。のぞいてみて下さい。リンクしています。